目次
はじめに
思考と言葉は切っても切り離せないものである。
にもかかわらず、思考法や発想法と謳われている書籍ではそのことにはほとんど触れられていない。
考える力を高めるのであれば、言葉の特性を知り、意識的に操れるようになる必要がある。
あなたにはこれから言語学や音声学、意味論などの分野から思考に関する部分のみを知ってもらい、言葉に対する見方を変え感度を高めてもらおう。
そうすることで、基本姿勢である「これからは言葉を武器として使ってやろう」という意識が芽生えていくはずだ。
さあ、深淵なる言葉の世界に飛び込もう。
言葉とは人間とその他の動物とを分かつもの
すでにあなたもお気づきであろうが、人は言葉を使って思考している。
そして、その言葉を使えるのは地球上で人だけである。
人は言葉を得て進化をとげてきたことにより食物連鎖の頂点に君臨することができ、あらゆる生物をその支配下においた。
それほどまでに言葉の力はとてつもなく強大で偉大なものなのだ。

人間以外の生き物からすると、言葉はきっと魔法のような代物に違いない。
また、その場にいない者に物事を伝達することも可能であるし、伝えた事柄を何度でも引用することができる。
しかし、誰もが当たり前のように言葉をつかって生きている現代において、私たちはこの強大さや偉大さに気づいていない。
もちろん言葉に関していえば、あなたが日本人なら間違いなく学生時代に母語である日本語を国語という科目を通してその大切さを学んできているだろう。
そして、心の中にいくぶんか言葉って大切だなと思っているかもしれない。
だが、その程度の考えや感覚はあまりにも浅すぎる。
繰り返すが、「言葉は私たちの知力の根源」なのだ。

言葉(数も言葉の一種である)が無ければあなたの手元にあるスマホやパソコンも存在していない。
だから、考える力を高めるには今の考えや姿勢を改め、言葉を深く理解し、磨きあげることが絶対に必要になる。
そして、それは学生時代の国語の勉強だけでは全く足りていない。
なぜなら学生時代に学んだ国語の内容と思考についての言葉の勉強とは目的が異なり、内容も異なるからである。
だから学校の先生は国語を教えられても、考える力を高めることを教えられない。(※もちろん、国語は母語の基本な使い方を学ぶ非常に重要なものだ)
考える力を高めるには、心理学や言語学、脳科学などの多岐にわたる分野に対し「いかに考える力を高められるか?」という軸で横断的に研究する必要があるのだ。
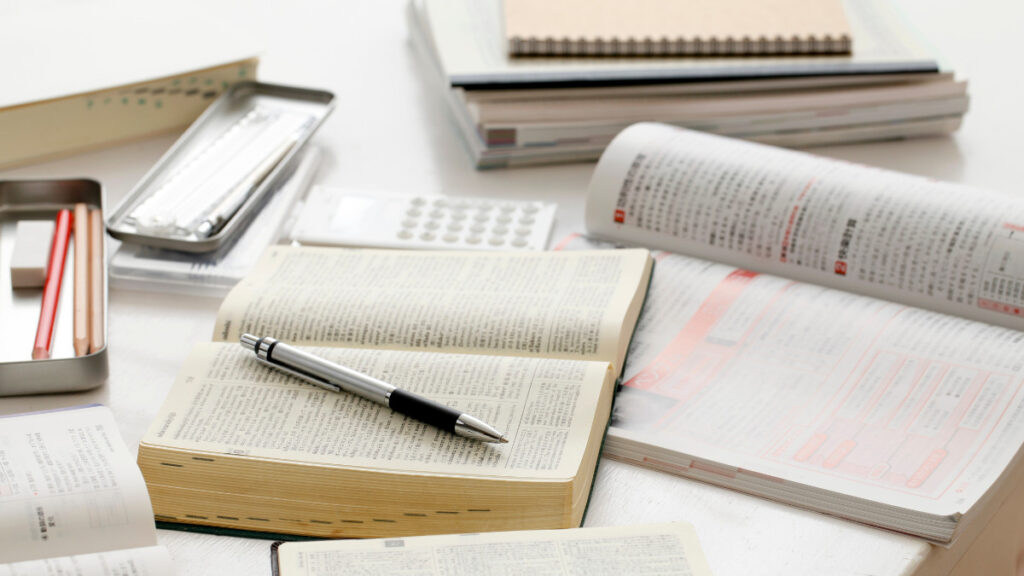
これからあなたにお伝えする内容は自身の思考を操るための最も基礎となるものだ。
思考を意図的に操ることができるようになれば、思考の方法や手順そのものを自ら生み出すこともできるようになる。
結果、「何を考えていいのかわからない」「どういう風に考えていいのかわからない」「何から考えていいのかわからない」などといった状態・状況を脱することができるようになる。
そして、それが適切かつ論理的であれば正しい結論を導くことができ、あなたが望む結果を得られる可能性を高められる。
では、そのためにはどうすればよいか?
そのためには原理原則、本質を学ぶ必要がある。
だからあなたには基本的にお手軽・即席的なものはお伝えするつもりはない。
それでは応用が効かないし、初めて出くわすシーンではお手軽ノウハウが使えないので、そこから先に進めず路頭に迷うだろう。
だから原理原則を学ぶことで初めて身につく応用力をつける必要があるのだ。
ーー前置きは、このぐらいにしておこう。
このブログを見てくれているあなたには誰よりも早く言葉の本質を学び、習熟することで圧倒的な優位性を手にしてほしい。
それがあなたの力となり、未来を自ら切り開くお手伝いができるなら望外の喜びである。

言葉とは音である
さっそく言葉の原理原則をあなたには学んでもらおう。
おそらく、言語学や認知科学などを勉強していなければ、考えたことはないだろうが、
言葉とは音の連続がある意味を表したものである。
もしかすると、言葉は「文字」というカタチから始まったと思っていた人もいるかもしれないが、そうではない。
言葉はまず音というカタチで生まれ、その後に文字が発明されたのだ。
その証拠に、世の中には6500以上の言語があるが、そのうち6000は音だけで文字がない言語なのである。
また、別の機会に説明するが、この「文字」の発明も人類にとてつもない恩恵をもたらしたのだ。
なお、思考において利用する言葉は「内言(ないげん)」といい、音声化された頭の中の声である。
ちなみにこの内言とは心理学における概念である。
数年前に『ことばにできるは武器になる』(梅田悟司/日本経済新聞社)がベストセラーになったが、これはその内言についてフォーカスしたものだ。
著者の本業がコピーライターということもあって、やはり言葉に鋭敏な方は考える力が高いんだなと改めて考えさせられた。
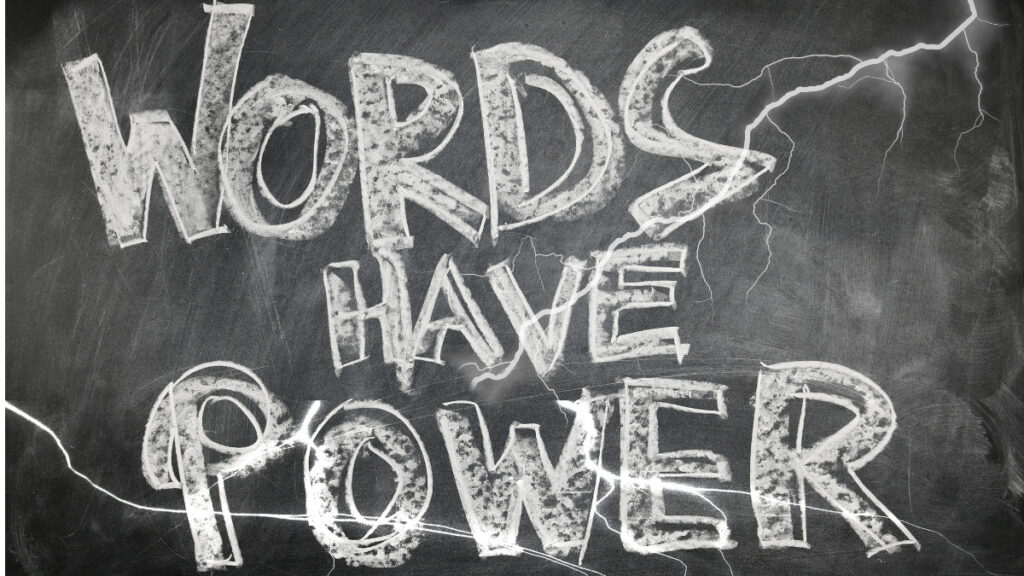
話しをもどそう。
言葉とは音の連続がある意味を表したものである。
例えば、「犬」は「い」と「ぬ」という音を組み合わせたものだし、「椅子」は「い」と「す」という音を組み合わせたものである。
全ての意味はこのように音の連続・組み合わせによって表される。
ちなみに上記のように意味を生み出す一音のことを言語学では「音素」という。
日本語には24の音素(母音5、子音16、特殊3)があり、この有限の音素を組み合わせることで森羅万象を表すことができる。
さらに説明すると、その音素同士が組み合わさると「音節」という単位になり、音節が連続してある物事(とその意味)を表すようになると「形態素」となる。
この形態素がいわゆる「単語」と呼ばれるものとほぼ等しく、言葉が意味を持つ最小単位になる。
そして、単語を組み合わせると「文」、文を組み合わせて「文章」というように段階的に複雑な構造体へと変化していくのだ。
例えば、「犬」「椅子」「平和」「政治」。
言葉を得た初期の人は、まず目の前に存在する固有の物事を指し示したり、特定するために「名前」をつけたと考えられる。
そして、そのうち固有の物事一つ一つに名前をつけていくと、キリがなく非効率であることに気づいたのだろう。
ある段階で無数にある固有の物事・事象の中からある共通する特徴をもったものをまとめ、それに名前をつけるようになった。
これがいわゆる「概念」というものである。
このことにより、自分の家のジョン、隣の家のポチ、友達の家のハチ、それらそれぞれ固有の動物を全て「犬」だけで表せるようになったのだ。
また、概念が生まれたことにより、現実世界の実物との分離を可能にし、頭の中にある精神世界で思考の材料として操れるようになった。
そして、さらに言葉は現実世界には物質として存在しない物事も表すようになった。
「平和」「政治」
これらは物質として存在せず、知覚できない概念だ。
こうして人は目に見えない世界(抽象の世界)も操れるようになったのだ。

ここまでお読みいただいて感謝致します。
ぜひ引き続き他の記事をお読みいただけると幸いです。

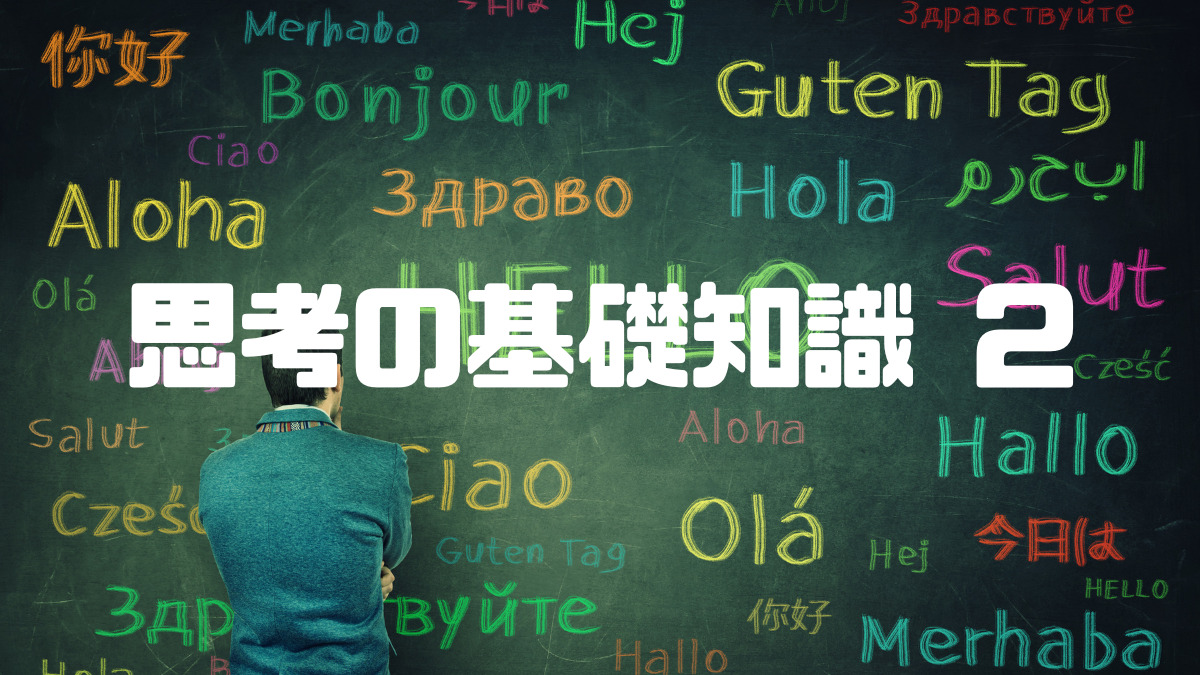

コメント